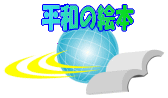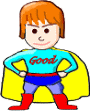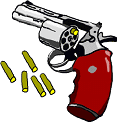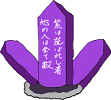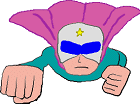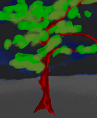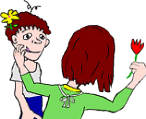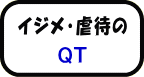
根っこからイジメ・虐待問題を考える
イジメの心理的原因としては、やはり善悪中毒を避けて通るわけにはいきません。 視点によって全く同じ行為が、悪との戦いになり、またイジメにもなるのです。 朋子さんの水彩画でお楽しみください。(@少し、残酷なシーンがあります。 @スマホの方は⇒こちら印刷版「魔法のメガネ」の方が読みやすいかも。)
善悪中毒はまるで条件反射のような心の癖として作られます。
何が何でも、悪ではなく善にならなければいけない。・・・これは多くの人々にとって強迫観念となっているようです。 この強迫観念は、たとえばこんな心理の流れからも形成されるでしょう。
多くの人々が強迫観念を共有すれば、それは増幅され、「現実」となるでしょう。
苛められないために、もっとも手っ取り早い方法は、苛める側に立つことです。 この心理が、イジメの発見を遅らさせ、またエスカレートさせると考えられます。 苛めることを拒否し、自分もまた苛められる危険に直面するか。それとも苛める側に立ち、当面の身の安全を図るか。 この選択は、時に大変深刻なものとなるでしょう。
固定化した被害者意識もまた、イジメ問題の解決を難しくするでしょう。
いじめ問題を、「イジメは悪。虐めっ子は悪い子」といった単純な構図でとらえても、その心理・原因を理解することは 出来ません。虐めっ子もまた、正義のために戦っているのかもしれない、そんな可能性をご理解ください。
次の二つの絵本は、イジメの原因としての善悪の働きを浮き彫りにするものです。 絵本「友達になれるよ」は善悪が無く、イジメも無い場合です。 絵本「僕はイジメっ子?」は善悪が有り、イジメが生まれる場合です。 比較してご覧下さい。
罰しているつもりが、実質的にイジメとなることもあるでしょう。 こちらは「罰と恐怖の絵本集」の1作品です。
「仲良くしなさい」という命令が、イジメを生むこともあるでしょう。愛は命令では生まれません。
命令で愛が生まれるという誤解は、虐待の原因にもなるのです。次の絵本は子供への虐待がテーマです。
同じ錯覚から性的な虐待も生まれます。
これでイジメ・虐待問題に関するクイックツアーは終わりです。 こうした絵本を親子で話し合うときのキッカケ、学校のホームルームの教材など、状況に応じてご活用いただければ嬉しいです (参考 教育者の方へ ―平和の絵本を道徳教材としてご利用下さい)。 商業目的を除き、コピーはご自由にどうぞ(朋子さんの絵はコピー不可です。僕のオリジナルをご利用下さい)。印刷しやすいようにPDFファイルも用意してあります。
さて、この平和の絵本集には、この他にも引きこもりや戦争・心の悩みなど、様々なテーマの絵本がたくさんあります。 お時間があるときに、じっくりと他の絵本もお読みになって頂ければ嬉しいです。
ありがとうございました。
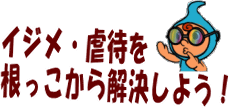
平和の絵本
世界平和の絵本集(WEBトップ頁)クイックツアー-QT
お母様へ(子供を心の病から守る)-QT 悩み落ち込む方へ-QT イジメ・虐待問題-QT 政治・社会問題-QT 戦争と平和-QT 国を憂う方へ-QT
絵本集
本当に悪いのは誰? 世界を巡る攻撃命令 正しいことって何? 攻撃命令無制限
殴れるよ 見下せるよ 誤魔化せるよ
良い子にならなきゃ(地獄の恐怖) やるかやられるか パブロフの犬(条件反射の心理学)
子供を犯罪者に(少年犯罪の原因) 教育マシン(子供の教育に) どっちだ?(孤独の心理)
悪いことは悪い 二重に隠れて 大事な議論 正義の味方
サングラス(理想主義の罠) 出ていて引っ込んでいるもの 認識のパターン(絵本集)
終わりの無い物語(憎しみの連鎖) 私は悪い人間です(罪と祈り)
魔法のメガネ(いじめや戦争) 見えない危険(軍拡の心理) 怯える人々(恐怖で狂暴に) 負けるものか(意志が弱い方へ)
善悪と愛憎 愛と嘘(嘘と偽善) 愛と敵(虐待へ) 愛を命令しないで(オムニバス絵本)
神と善悪 悪人さん、ありがとう 失敗し続ける方法(オムニバス絵本) バカ自慢-絵本集 怒りと憎しみ -絵本集
悪と罰(罰の心理) ある星の飲酒運転(酒酔い運転防止) 罰とイジメと自殺のロンド 罰と恐怖(絵本集)
愛する人が殺されたら―復讐の相手 復讐の相手-Ⅱ 想像という現実(連作絵本) 嫌な気持ちになる絵本 それぞれの深い望み
嵐と湖(心の悩みへ) 待って(焦りと不安へ) 国破れて
生と死(絵本集) お金と経済(絵本集) 民主主義(絵本集)
リンゴ異文化騒動記 僕らは特別(被害者意識) 一輪の花(原爆の廃絶) 差別について(絵本集) 日本独立の選択
平和の絵本理論書
善悪中毒の心理学/善悪という怪物
ボランティア
ボランティアのお願い -寄付のお願い -協賛企業 -リンクのお願い
絵本の運動について
平和の絵本の運動 -平和の旅(絵本の贈り先) -キャンペーン -メッセージ広告 -善悪の心理テスト -活動方針 -活動の記録 -メルマガ
イラスト
イラストレーターが描く平和の絵/絵本 イラストレーター公募(絵の書き直し)
メッセージ/手紙
平和のメッセージ集 「和」とは? 精神世界の旅人へ(気づきと戦争) 教育者の方へ(道徳教材) 心の癒しへ 世界平和を願う方(反戦運動へ) 憂国の侍へ -人種平等決議案 -市丸少将の手紙
平和の絵本について
和を地球へ(私どものご紹介) お問い合わせ(感想/メッセージ) リンク集 サイトマップ
管理サイト
平和の絵本から、ありがとう 活動日誌 Diary & LettersPeace Picture Books ユーチューブ(絵本の読み聞かせ) 平和の絵本のFBファン頁 PeacePictureBooksFB fan page ツイッター
平和の絵本のメルマガ登録